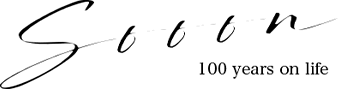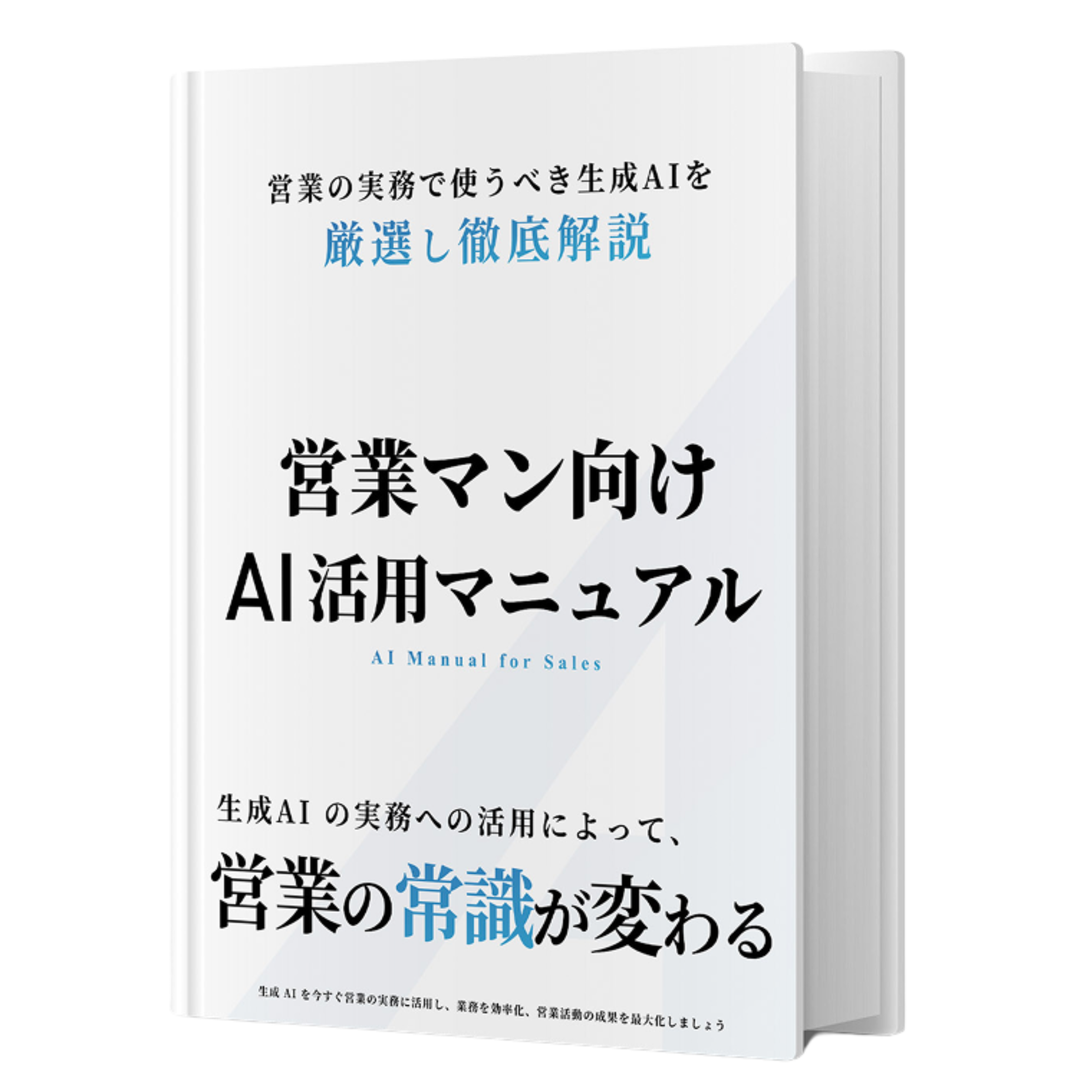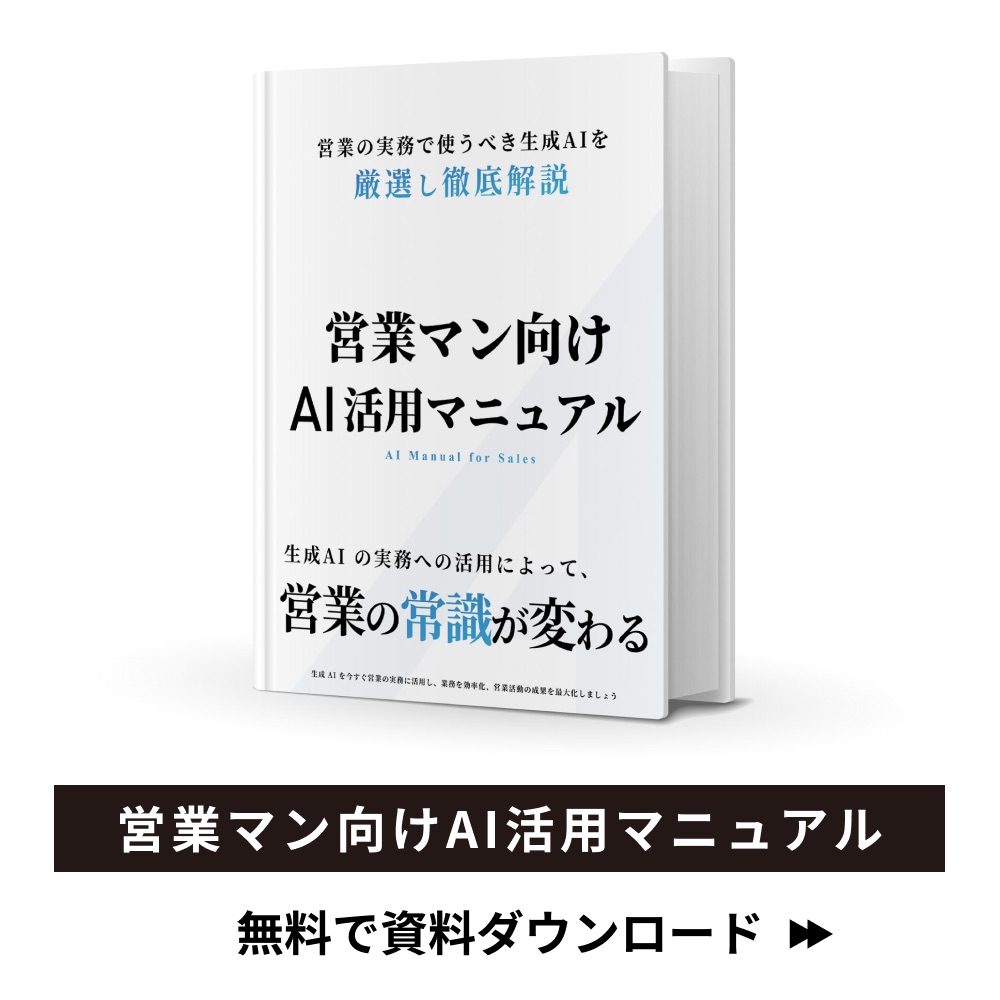バックオフィス業務を自動化するには?導入すべきツールや事例を紹介

「バックオフィス業務を自動化する方法は?」
「どんな業務を自動化できる?」
「バックオフィスの業務効率化でおすすめのツールや成功事例を知りたい」
バックオフィスとは、経理・財務・法務・総務・庶務・人事など、顧客とは直接的に接することがない業務や部署を指します。
営業職のように、直接利益を生み出すわけではありませんが、企業を影から支える重要な役割を担っており、組織の円滑な運営には欠かせない存在です。
しかし、近年は人手不足の影響から、従業員の負担が増大している企業も多いのではないでしょうか。バックオフィス業務は事業の継続に不可欠であり、早急な対策が求められます。
そこで本記事では、バックオフィス業務の課題を深掘りしながら、業務を自動化する方法・役立つツール・成功事例などを詳しく解説します。
この記事を読めば、バックオフィス業務を自動化する重要性が理解でき、これから何をすべきかが明確になります。ぜひ参考にしてみてください。
バックオフィス業務の自動化が重要な5つの理由
バックオフィスは利益に直結しない業務とされることが多く、これまで業務効率化の優先順位が低くなりがちでした。
しかし近年、バックオフィス業務の自動化が注目を集めています。
その背景には、以下5つの課題が挙げられます。
- 人手不足が加速している
- 業務の属人化が深刻化している
- 膨大なアナログ業務でヒューマンエラーが発生しやすい
- 他部署との連携に追われて本来の仕事に注力できない
- 問い合わせ対応の負担が大きい
順番に解説します。
1.人手不足が加速している
まず挙げられる課題が、人手不足が加速していることです。
マネーフォワードクラウドERPが2024年3月に実施した「バックオフィスのシステム導入に関する意識調査」によると、法人事業者608名のうち33.5%がバックオフィス業務の課題として「人手不足」を挙げており、最も多い回答結果となりました。
日本では、少子高齢化の影響により労働人口が減少し続けています。そのため、人材を確保したくても採用コストが高く、十分な人員を確保するのが難しい状況が続いています。
結果、従業員一人ひとりにかかる負担が増大し、長時間残業や精神的負担の増加につながっている企業も多いでしょう。
2.業務の属人化が深刻化している
慢性的な人手不足により、長年、同じ社員が特定の業務を担当しているケースは少なくありません。
その結果、業務の属人化が深刻化している企業も多いのではないでしょうか。
特にバックオフィスでは、経理や財務、法務など専門的な知識を必要とする業務が多く、さらに企業独自の手続き方法が存在する場合もあります。
このような専門性の高い業務は、担当者の交代が難しく「あの人がいないと対応できない」といった状況が生まれやすいです。
もし担当者が急に退職したり、長期休暇を取得したりすると、業務が滞ってしまうかもしれません。したがって、バックオフィス業務においても標準化が重要になるでしょう。
3.膨大なアナログ業務でヒューマンエラーが発生しやすい
バックオフィスは、書類作成や押印などアナログ業務が多い傾向にあります。
アナログ業務は、時間や場所に縛られやすいことや細かい確認が必要であることから、業務スピードを高めるのに限界があります。
その結果、担当者の残業時間や精神的なストレスが増え、疲労や確認作業の煩雑さにより、ヒューマンエラーが発生しやすくなるのです。
ミスが起きると修正作業に時間を取られ、他の業務に支障をきたす可能性があります。よって、担当者の業務負担軽減が求められるでしょう。
4.他部署との連携に追われて本来の仕事に注力できない
バックオフィスは、フロントオフィスの支援を主な役割としているため、他部署との連携が多いのが特徴です。
例えば、事務手続きや経費申請、備品整備など、さまざまな業務で他部署とのやり取りが発生します。
その結果、連絡業務に多くの時間を取られ、本来のバックオフィス業務に十分な時間を確保できないケースも少なくありません。
本来の業務が終わらないことで残業時間が増え、モチベーション低下につながることもあります。また、業務を早く終わらせようと焦るあまり、手続きが煩雑になったり、ミスが発生したりするリスクも考えられるでしょう。
5.問い合わせ対応の負担が大きい
バックオフィスでは、他部署との連絡だけでなく、社内からの問い合わせ対応も重要な業務のひとつです。
特に、繁忙期や年末調整の時期には問い合わせが集中し、担当者は本来の業務を中断して対応しなければならない場面も少なくありません。
その結果、以下の事態を招く要因にもなります。
- 長時間労働の増加
- 業務効率の低下
- 担当者のモチベーション低下
このような課題を解決するには、簡単な問い合わせへの自動対応システムの導入や、FAQ(よくある質問)の整備など、社員が自己解決できる仕組みを構築することが重要です。
バックオフィス業務を自動化する4つのメリット

バックオフィスの業務効率化は軽視されがちですが、自動化することで、以下4つのメリットにつながります。
- 企業全体の生産性向上につながる
- 人件費や保管コストを削減できる
- 入力ミスや抜け漏れを防止できる
- 従業員のモチベーションアップが期待できる
順番に解説します。
1.企業全体の生産性向上につながる
バックオフィス業務を自動化すれば、会社全体の生産性向上につながります。
例えば、手作業でおこなっていたデータ入力や書類作成、請求書発行などの定型業務を自動化することで、ヒューマンエラーを大幅に削減できます。これにより、手戻りや修正作業が減るでしょう。
また、ロボットやシステムは人間よりも速く正確に処理をおこなえます。これまで時間をかけていた作業が短時間で完了することで、担当者は他の業務のサポートに回れます。
さらに、定型業務から解放された担当者は、より創造性や判断力を必要とするコア業務に集中できるようになります。
例えば、業務改善提案や企画立案、複雑な問い合わせ対応などに時間を割けるため、組織全体の生産性アップに寄与するでしょう。
2.人件費や保管コストを削減できる
バックオフィス業務の自動化は、人件費や保管コスト削減にもつながります。
先ほどお伝えした通り、データ入力や書類作成、請求書発行などの定型業務はロボットやシステムのほうが速く正確にこなせます。
これまで人がおこなっていた定型業務を代替することで、その業務に必要だった人員を削減可能です。さらに、担当者への業務負担が軽減されることで、余計な残業時間を減らすこともできます。
また、書類作成や管理をデジタル化することで、紙の書類が不要になります。書類を保管するための物理的なスペースをなくせるため、保管コストも削減できるでしょう。
3.入力ミスや抜け漏れを防止できる
これまで手作業でおこなっていたデータ入力や転記作業を自動化すれば、入力ミスや抜け漏れの防止もできます。
人間は疲労や体調不良、集中力の低下などで、どうしてもヒューマンエラーが発生しがちです。どれだけ優秀な社員であっても、長時間の残業や私生活の影響によってミスを犯してしまうことはあります。
しかし、ロボットやシステムは、疲労や体調不良などの影響を受けることがありません。いつでも一定の品質を保つため、入力ミスや抜け漏れのミスを防止できるでしょう。
4.従業員のモチベーションアップが期待できる
バックオフィス業務を自動化することで、従業員のモチベーションアップも期待できます。
その理由は、以下の通りです。
単調な作業から解放され、やりがいのある業務に時間を使える
残業時間が削減され、ワークライフバランスを維持しやすくなる
ヒューマンエラーが解消され、精神的な負担が軽減される
業務がデジタル化され、リモートワークを導入しやすくなる
バックオフィスを自動化すれば、従業員にとって働きやすい環境が整います。これにより、従業員のモチベーションが向上し、組織全体の生産性も向上するでしょう。
また、従業員一人ひとりが意欲的に業務に取り組むことで、企業全体の活性化につながり、より優れたビジネス成果を生み出しやすくなります。
バックオフィス業務を自動化すると仕事がなくなる?
「バックオフィス業務が自動化されると、いずれ仕事がなくなるのでは……」と懸念されている方もいるかもしれません。
しかし、自動化されるのは、あくまでも「規則性のある単純作業」です。バックオフィスには人間の判断を必要とする業務も多く、完全に仕事がなくなることはないでしょう。
バックオフィスの自動化によって「なくなる可能性のある仕事」「今後もなくならないと考えられる仕事」の例は、以下の通りです。
自動化でなくなる可能性がある仕事
今後もなくならないと考えられる仕事
- 給与計算
- 伝票や仕訳の入力
- 勤務データの集計
- 備品管理
- 簡単な問い合わせ対応
- 税務関連の高度な対応
- イレギュラーな経理処理への対応
- 財務分析
- 経理システムの管理
- 帳簿や決算書類の最終確認
ロボットやシステムの導入は業務効率化に役立ちますが、バックオフィス業務のすべてを代替できるわけではありません。
単純なルーチンワークは自動化に効果的ですが、高度な専門知識や判断力が求められる業務は、人間の手が必要です。
自動化が進むことでバックオフィス部門の役割は、単なる事務作業から「専門知識を活かした意思決定のサポートや戦略立案など」に変化していくと考えられます。
バックオフィス業務の自動化に役立つツール4選

バックオフィス業務の自動化に役立つツールには、以下の4つが挙げられます。
- RPA
- iPaaS
- OCR
- AIチャットボット
順番に解説します。
1.RPA
RPAとは、Robotic Process Automation(ロボティックプロセスオートメーション)の略で、ソフトウェアロボットによって業務を自動化することを指します。
ロボットは規則性のあるルーチンワークの繰り返しを得意としており、人間ではミスが生じる業務も安定して進められます。
また、24時間365日稼働でき、夜間や休日も業務をこなせます。担当者は最終確認をするだけで済むため、業務効率化や人員コストの削減に大きく貢献するでしょう。
なお、主なRPAツールは、以下が挙げられます。
- WinActor
- アシロボ
- RoboTANGO
2.iPaaS
iPaaS(アイパース)とは、Integration Platform as a Serviceの略で、複数のサービスやアプリケーションを連携させるサービスのことです。
例えば、オンプレミス型(自社運用)のシステムと、クラウド型(外部提供)のアプリケーションをスムーズに接続し、データ移行や同期を自動化する役割を担います。
企業が異なるサービスを別々に利用していると、データが各システム内に分散し、担当者は確認作業に大きな手間と時間を取られることがあります。
しかし、iPaaSを導入することで、システム間のデータ連携をシームレスにし、業務の効率化や情報の一元管理を実現できます。
これにより、データの入力ミスや転記作業の負担を軽減し、業務のスピードと正確性を向上させることが可能です。
なお、主なiPaaSには、以下が挙げられます。
- JOINT iPaaS for SaaS
- JENKA
- BizteX Connect
3.OCR
OCR(光学的文字認識)とは、Optical Character Recognitionの略で、手書きや印刷された文字をデジタルデータに変換する技術のことです。
例えば、紙の資料や名刺をスキャナーで読み取ることで、デジタルデータとして保存・編集できるようになります。
手作業によるデータ入力の負担が大幅に削減されることで、業務効率化や入力ミスの防止に貢献するでしょう。また、書類のデジタル化により、保管コストの削減にもつながります。
近年では、AIを活用したOCR技術も進化しており、手書き文字やかすれた印字の認識精度が向上しています。レイアウトを保持したままデータ化することも可能です。
入力作業の効率化や書類保管コストの削減を目的にする場合は、OCRツールを導入するとよいでしょう。
なお、AIを活用したバックオフィス向けOCRツールは、主に以下が挙げられます。
- AnyForm OCR
- DEEP READ
- eas
4.AIチャットボット
AIチャットボットとは、人工知能技術を用いて、人間との対話を自動化するサービスです。
例えば、問い合わせ対応に導入すると、事前に学習させた社内データや過去の対応履歴をもとに、最適な回答を自動生成します。
「簡単な質問には即座に自動対応」「複雑な内容の場合は担当者へスムーズに引き継ぎ」が可能なため、バックオフィスにおける問い合わせ対応の負担を大幅に軽減できます。
特にバックオフィスには、総務・経理・社内システム関連など、従業員からの似たような問い合わせが多く寄せられる傾向にあります。
そのため、AIチャットボットを導入することで、担当者が繰り返し対応する手間を削減し、本来の業務に集中できる環境が整うでしょう。
なお、バックオフィス向けAIチャットボットサービスは、主に以下が挙げられます。
- OfficeBot
- PKSHA AI ヘルプデスク
- チャットプラス
自動化できる主なバックオフィス業務7選

自動化できるバックオフィス業務としては、主に以下の7つが挙げられます。
- 経費精算
- 勤怠管理
- 給与管理
- 帳票管理
- 採用管理
- 人事評価
- 従業員からの問い合わせ対応
順番に解説します。
・1.経費精算
経費精算は、従業員が業務で立て替えた費用を会社に申請して払い戻しを受ける業務です。
人間が手作業でおこなう場合、以下の業務が必要になります。
- 申請書の作成と提出
- 領収書の確認と承認
- 会計システムの入力
これらを手作業でおこなうと、以下のデメリットにつながるでしょう。
- 担当者に多くの手間と時間がかかる
- 入力ミスや確認のミスが発生する
- 申請書や領収書の保管・管理コストがかかる
しかし、経費精算システムやOCR付き会計ソフトなど導入すれば、交通系ICカードのデータ取り込みや領収書のスキャンなどで、業務を自動化できます。
2.勤怠管理
勤怠管理は、従業員の出退勤時間や休暇取得状況などを記録・管理する業務です。
タイムカードの集計や手入力による管理は、ミスも発生しやすく、担当者に大きな負担がかかってしまいます。
しかし、勤怠管理システムを導入すれば、集計や入力の業務を自動化できます。
これにより、担当者の負担が軽減されるだけでなく、労働時間や休暇取得の状況をリアルタイムで把握できるようになります。
3.給与管理
給与管理は、従業員の働きを正確に給料へ反映する大切な業務です。
主に、以下の業務をおこないます。
- 給与計算
- 明細書の発行
- 税金や社会保険料の控除
- 振込手続き
給与管理の担当者には、複雑な計算や法改正への対応が求められます。専門知識を要するため、業務の属人化につながりやすいのが課題です。
しかし、給与管理ソフトを導入すれば、複雑な計算を自動化できます。計算ミスを防止することで、担当者への精神的負担を大幅に軽減可能です。
さらに、法改正に合わせてシステムを自動アップデートする機能も備わっているため、属人化の解消にも貢献するでしょう。
4.帳票管理
帳票管理は、企業活動で発生するさまざまな帳票の作成・送付・保管をおこなう業務です。
例えば、以下のような帳票を取り扱います。
- 見積書
- 請求書
- 納品書
- 領収書
- 入出金伝票
- 振替伝票
- 仕訳帳
- 出納帳
- 買掛帳
- 売掛帳
これらをすべて紙ベースで処理・管理していると、入力ミスや紛失のリスクがあります。保管コストもかかるでしょう。
しかし、販売管理システムや請求書発行システムなどを導入すれば、帳票の自動作成やデジタル管理ができるようになります。よって、業務効率化やコスト削減につながるでしょう。
5.採用管理
採用管理は、自社が求める人材を確保するために、採用活動の計画・管理をする業務です。
主に、以下の業務を担当します。
- 求人情報の掲載
- 応募者の受付
- 書類選考
- 面接日時の調整
- 内定通知
多くの情報を取り扱うため、担当者に大きな負担がかかり、業務が煩雑になりやすいという課題があります。
しかし、採用管理システムを導入すれば、応募者の情報を一元管理が可能です。選考状況の可視化や、応募者への自動連絡などにより、担当者の負担軽減につながります。
採用担当者は定型業務から解放されることで、より戦略的な業務や応募者とのコミュニケーションに集中できるでしょう。
6.人事評価
人事評価は、従業員の業績や能力を評価し、給与や昇進へ反映させる業務です。
給与や昇進は従業員のモチベーションに大きく影響するため、評価基準の設定や結果の集計、適切なフィードバックが重要になります。
しかし、人間が手作業で業務を遂行していると、以下のような課題が発生しがちです。
- シートの準備に手間がかかる
- 評価のばらつきが起きやすい
- データを有効活用できない
その点、人事評価システムを導入すれば、各種テンプレートを使って評価シートの作成ができます。また、配布・回収・集計も自動化可能です。
さらに、客観的な数値から評価が可能になることで、業績や能力に応じた公正な評価をおこなえます。これにより、従業員のモチベーション向上が期待できるでしょう。
7.従業員からの問い合わせ対応
バックオフィスでは、従業員からの問い合わせ対応も重要な業務のひとつです。
特に、以下のような問い合わせが頻繁に寄せられます。
- 勤怠や業務に関する質問や要請
- 社内システムの使い方やトラブル対応
- 有給・産休・育休の取得方法の確認
- 交通費・出張費・接待費などの経費申請方法の確認
これらの問い合わせは、回答パターンが決まっていることが多く、同じような対応を繰り返すことが担当者の負担になりがちです。
しかし、AIチャットボットやFAQシステムを導入すれば、よくある質問への自動回答が可能になります。
担当者の直接対応が減ることで、問い合わせ対応の負担を軽減し、業務の効率化につながるでしょう。
バックオフィス業務の自動化に成功した事例4選
ここからは、バックオフィス業務の自動化に成功した4つの事例を見ていきましょう。
1.KDDI株式会社|作業時間を92%削減しミス率ゼロを実現

KDDI株式会社は、RPAツーの導入でバックオフィス業務の効率化を実現させています。
同社では、銀行の入出金データ(約9,000件/日)の抽出・消込業務をおこなっていますが、繁忙期は入力作業の負荷が高く、10名以上を増員しても処理ミスが発生していました。
しかし、RPAツールを導入したところ、作業時間が92%削減され、ミス率ゼロを実現したと報告されています。
参考:KDDI様 RPAツール導入でバックオフィス業務の高効率化を実現|アルティウスリンク株式会社
2.帝人株式会社|バックオフィスへの問い合わせを20%削減

帝人株式会社では、チャットボットを活用してバックオフィスへの問い合わせ業務を自動化しています。
同社には多くの事業本部やスタッフ部署があり、各部署はそれぞれ社内イントラサイト(専用のWebサイト)を構築していました。
しかし、人事や総務に関する情報が各イントラサイトに散在することで、従業員は「求める情報が見つけられない」と悩み、バックオフィスに電話やメールが集まっていました。
その結果、問い合わせた従業員はオフィスの業務時間外には回答を得られず、業務を中断せざるを得ない状況となっていたようです。
また、バックオフィス担当者も、同じような問い合わせが何度も寄せられることで、精神的な負担が大きくなっていました。
そこでAIを搭載したチャットボットを導入。FAQ(よくある質問)を自動生成する仕組みを構築した結果、従業員の自己解決能力が向上し、バックオフィスへの問い合わせが20%削減されたと報告されています。
参考:バックオフィスへの問い合わせを自動化! 成功の鍵はナレッジ活用!|OfficeBot
3.株式会社トーシン|請求業務にかかる時間を3日→3時間に削減

株式会社トーシンでは、請求業務に自動システムを導入して業務効率化を実現しています。
同社は、受注や請求に関わる事務作業をすべて手作業でおこなっていました。
しかし、手作業ではヒューマンエラーが起こることが多く、納品書の作成に時間がかかることで配送時間に遅れが出ることもあったそうです。
そこで受発注の自動システムを導入しました。
手書き業務を自動化することで、受注管理の作業時間は1日2〜3時間ほど削減。請求書発行については、3日かかっていた業務が3時間に短縮されたと報告されています。
参考:株式会社トーシン青果 様 請求業務にかかる時間が3日→3時間に!手作業によるミスや伝票の管理コストも大幅に削減|CO-NECT株式会社
4.株式会社ハンナ|AI-OCRの活用でバックオフィスの属人化解消
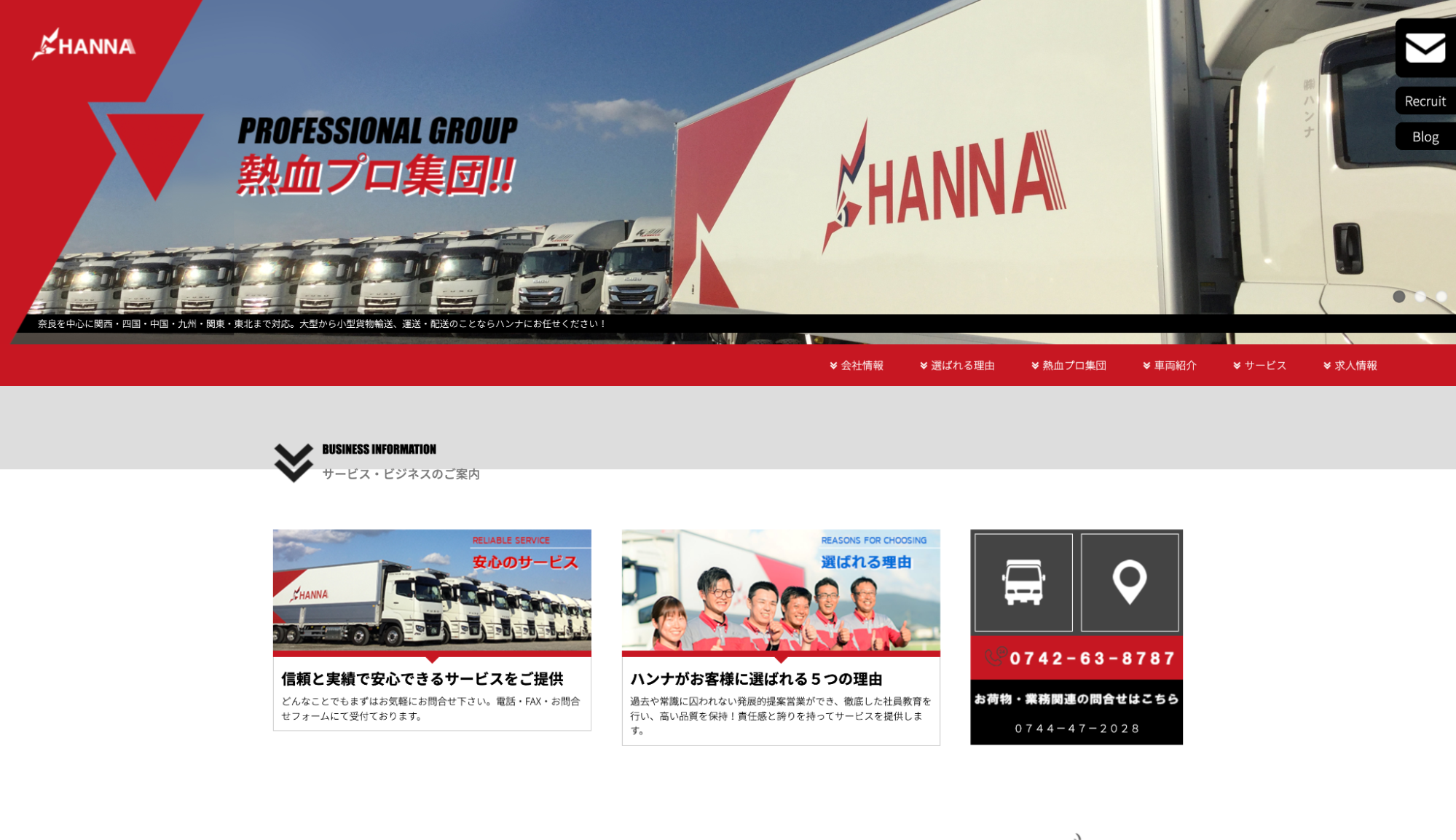
株式会社ハンナでは、AI-OCRの活用でバックオフィスの属人化を解消しています。
同社では、バックオフィスの労務時間管理や日報などの資料管理において、担当者のパソコンスキルに依存していることに課題を抱えていました。
しかし、AI-OCRの導入後は、入力作業や確認作業で起こっていたミスがなくなり、誰が担当しても安定した業務をこなせるようになったそうです。
その結果、有給休暇の完全取得や労働時間の短縮を実現し、社員のモチベーション向上につながったと報告されています。
参考:AI-OCRの活用でバックオフィスの属人化解消!|船井総研ロジ株式会社
バックオフィス業務の自動化を成功させる3つのポイント
バックオフィス業務を自動化させる際には、以下3つのポイントが重要です。
1.目的や予算に合ったツールを選ぶ
バックオフィス業務と一口に言っても、その範囲は多岐にわたります。経理・財務・法務・総務・庶務・人事など、企業によって注力したい業務や課題は異なるでしょう。
そのため、自動化を検討する際には「どの業務の何を自動化したいのか」を明確にすることが大切です。
目的が曖昧なままツールを導入してしまうと、機能を使いこなせず、期待した成果を得られない可能性があります。
また、自動化ツールを導入・運用するには費用がかかります。初期費用だけでなく、月額利用料、保守費用なども含めて、予算と目的を照らし合わせることも大切です。
2.ツールの運用体制を整備する
適切なツールを選択したとしても、その後の運用体制が整っていなければ、従業員が使いこなせない可能性があります。
例えば、高機能なツールを導入しても「操作方法が複雑でわからない……」となれば、仕方なく手作業で業務を遂行することになるかもしれません。
また、担当者による運用のばらつきが生じると、データ入力や管理方法において、思わぬトラブルが発生するリスクもあります。
そのため、ツールを導入する際は、事前に運用体制を整備しておく必要があります。具体的には、以下を整備するとよいでしょう。
- 担当者や責任者を明確に指名する
- データ入力や管理方法のルールを定める
- 操作手順や設定方法などのマニュアルを作成する
- 担当者に対して研修を実施する
業務を効率化させるには、スムーズな運用体制の構築が不可欠です。従業員の抵抗感を減らし、積極的にツールを活用してもらうようにしましょう。
3.定期的に効果測定をする
ツールの運用を開始したら、定期的に効果測定をし、改善につなげていくことが重要です。
効果測定をおこなわなければ「なんとなく便利になった気がする」といった曖昧な評価しかできません。
その結果、実はあまり効果が出ておらず、運用コストだけがかかっていることに気がつかない可能性があります。
ツールの効果測定をする際は、導入前に設定した「自動化によって何を期待するのか」を基準に、具体的な指標を決めるとよいでしょう。
例えば、以下の通りです。
- 特定の業務にかかる時間がどれだけ削減されたか
- 削減された業務時間によって、どれだけ人件費が削減されたか
- 自動化によって、人的ミスの発生件数がどれだけ減少したか
- 業務の負担が軽減されたことで、従業員の満足度が向上したか
これらの指標を月ごと、もしくは四半期ごとに測定し、導入前と比較することで、ツール導入のコストパフォーマンスを評価できます。
もし期待した効果が得られていない場合は、その原因を分析し「従業員への追加教育」や「業務フローの見直し」などの改善策を検討する必要があります。
PDCAサイクルを回していくことで、バックオフィスにおける自動化効果を最大限に高められるでしょう。
まとめ:バックオフィス業務を自動化して企業競争力を高めよう
バックオフィス業務は「利益に直結しない」という認識から、これまで業務効率化の優先順位が低くなりがちでした。
しかし、フロントオフィスの業務を円滑に進めるためには、経理や法務といったバックオフィス業務の働きが不可欠です。
特に、複雑な計算や専門知識が求められるバックオフィス業務は属人化が進みやすく、担当者の不在や退職によって業務が滞るリスクを常に抱えています。
したがって、企業の持続的な成長を実現するためには、バックオフィス業務の自動化が有効な手段となります。
RPAやiPaaS、AI-OCR、AIチャットボットといった自動化ツールを導入し、生産性向上やコスト削減につなげていきましょう。